クワガタの菌糸ビンって何だろう?幼虫が死亡するリスクもある
 少年
少年菌糸(きんし)ビンを使ったクワガタ飼育が流行っているみたいだけど、菌糸ってそもそも何だろう?
クワガタ飼育をしていると、必ず目にする機会が多くなる菌糸ビンです。
よくわからないま使っている方も多いみたいなので、少しだけ解説をしていきます。
この記事を読んでほしい人
- 菌糸がわからない
- 菌糸って何がいいの?
- 菌糸飼育のメリット・デメリットが知りたい
こんな疑問があるなら、ぜひ読んでいただきたい内容になっています。
 クワさん
クワさんちなみに筆者は、初めてオオクワガタの幼虫を購入したとき、菌糸でしか育てられないと勝手に思い込んでいましたw
ある程度の知識は大切ですね。
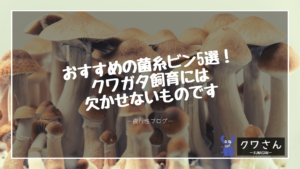
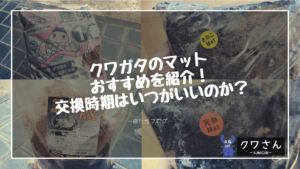
この記事を書いてる人

- 飼育種
■カブトムシ
ヘラクレス、サタン、ネプチューン、サンボンヅノなど(今後はカブトムシ系を拡大予定)
■クワガタ
メインは、ニジイロクワガタ、メタリフェルホソアカクワガタなど、色虫が基本好き - 飼育数
成虫・幼虫合わせて300匹以上、常時飼育中
茨城県日立市でカブクワのネット販売を行っています。
もし気になる生体などがおりましたら、お気軽にご連絡ください 。
最近はヤフオク!中心に出品をしています。
お問い合わせは、下記リンクよりお願いします。
そもそも菌糸ってなに?

 少年
少年菌糸って何?『菌』って名前についているってことは、ひょっとして人に害があるのかな?
菌糸は、オガクズにきのこ菌を繁殖させたものになります!
名前に菌とついていますが、人に害がある雑菌とは全く別物になるんですよ。
菌糸はきのこ菌なので、ボクたちが普段食べているきのことさほど変わりません。なので、人体には全く害はないんです。
 少年
少年なるほど!
でも、なんでクワガタ飼育にきのこが関係しているの?
木材は大きくセルロース、ヘミセルロース、リグニンの3つの成分で構成されています。ヘミセルロースがセルロースの周りを取り囲み、リグニンが接着剤のような働きで、その隙間を埋めることにより強固な構造になっています。
【木材分解のかぎをにぎるリグニン】
木材はリグニンが存在することで、微生物などによる分解を受けにくくなっています。倒木が分解されにくいのは構造が複雑で高分子のリグニンがあるからです。リグニンは木を守る天然の防腐剤だと考えられます。リグニンは、難分解性の成分で、もし人工的に分解しようとすると高温、高圧下のもとで様々な薬品を用い、多くのエネルギーを必要とします。
【リグニンを分解するキノコ】
自然界には、リグニンを分解できる生物種としてキノコがいます。キノコの中でも強い分解力を持つのが白色腐朽菌というキノコです。白色腐朽菌は、リグニンを分解することでセルロースなどの成分を栄養源とし、自らの菌糸をより広範囲に広げることができます。白色腐朽菌という名前は、白色腐朽菌が木材中の褐色成分であるリグニンを分解することにより木材が白く変色することから名づけられたものです。白色腐朽菌には、ヒラタケやシイタケといった一般的に栽培される食用キノコがあります
引用元:木の分解をたすけるキノコのリグニン分解酵素
簡単に説明をすると・・・
通常の木材だとクワガタはなかなか消化できないんですが、きのこ菌が木材を分解し朽ちさせることでクワガタが消化できるようになる。
ということです。
 クワさん
クワさん菌糸ビンはオガクズにきのこ菌を回しているものなので、クワガタが木材をバクバク食べることができる!つまりクワガタが大きくなりやすいってことなんです!
わかったかな・・・?
 少年
少年難しいけど、なんとなくわかった!きのこ菌は木材を分解し、クワガタが食べやすなるってことね!
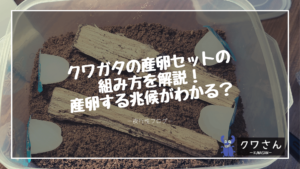
菌糸ビン飼育のメリットとデメリット

 少年
少年じゃあ菌糸ビンを使ってクワガタの幼虫を育てれば、大型のクワガタをバンバン目指せるってことだよね!菌糸ビン飼育が一番いいじゃん!
菌糸ビン飼育は、現在クワガタの飼育者の主流になってきてはいますが、メリットとデメリットがあるんです。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 大型を狙える 早く成長しやすい コバエが出にくい 交換時期がわかりやすい | マット飼育よりも費用が掛かる きのこが生えることがある 自分で菌糸をボトルに詰める場合は手間がかかる 幼虫が合わないこともある(死亡する) |
詳しく見てきます。
菌糸ビン飼育の『メリット』

菌糸ビンを使うことのメリットは何といっても、大型のクワガタが狙えることにあります!
大型が狙えるのでクワガタをブリードしている方のほとんどが菌糸を使っています。
※クワガタの種類による
一昔前は材飼育や発酵マット飼育が主流でしたが、菌糸ビンが使われるようになった近頃では、大型のクワガタがたくさん出るようになってきています。
もちろん菌糸ビンを使ったとしても必ず大型のクワガタになるわけではありません。様々な条件が揃って初めて大型を目指せるんです。
きのこ菌によっておがくずが分解され幼虫が食べやすくなるため、早く成長をしてくれるメリットがあります。
発酵マット飼育ではコバエに悩む方が多くいますが、菌糸ビン飼育では発酵マットに比べるとコバエが湧きにくいんです。
そして、菌糸ビンは幼虫が食べた後(食痕(しょっこん))や劣化が一目でわかるので交換時期がわかりやすいことも特徴と言えるでしょう!
 少年
少年こんなにメリットがあるんだね。
菌糸ビン飼育の『デメリット』

 クワさん
クワさんメリットがたくさんある一方でデメリットもあります。
菌糸ビンは、クワガタを大型が狙える大きなメリットがある代わりに、費用が高いです。
発酵マットは安いもので10Lで500円ほどですが、菌糸ビンは安くても800ml1本で300円~かかってきます。
少ない数のクワガタ飼育なら、菌糸ビンを使ってもそこまで負担にならないかもしれません。
しかし、10匹・20匹・100匹と増えると菌糸ビン飼育はかなりの出費になります。
菌糸ビンを大量に使う場合に費用を抑える方法として、菌床ブロックを購入しボトルに自分で詰めるやり方がありますが、手間と時間がかかります。
 クワさん
クワさん菌床ブロックは菌糸ビンで購入するより安いんです!
また、菌糸ビン飼育をしていると、一定の条件(温度や湿度)が揃うときのこが生えてきます。
画像のきのこはヒラタケになります↓↓

基本的に菌糸に使わているきのこ菌は『ヒラタケ』や『オオヒラタケ』、『カワラタケ』がほとんどで、人に害はありません。むしろ食べようと思えば食べれます。
きのこが生えて放置すると、ボトルの空気穴をふさいでしまうことや蛹室(ようしつ)の中にきのこが生えてしまうと羽化不全になることがあります。
きのこが生えていたらできるだけ取り除いてあげるようにしましょう!難しい場合には様子をこまめに確認しながら飼育してください。
デメリットの最後は、クワガタの種類によって菌糸ビンが合わない(死亡する)クワガタもいるということです。
詳しくは次章で解説をしていきます。
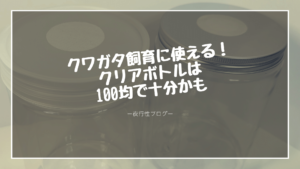
菌糸ビン飼育で幼虫が死亡する?

 少年
少年菌糸ビンを使って幼虫が死亡することってあるの?
実は、菌糸ビンは発酵マット飼育と比べると幼虫が死亡する確率が高い傾向にあります。
その理由として、以下のようなことが考えられます。
死亡にいたる原因
菌糸が合わない
そもそも菌糸が合わない場合があります。
発酵マットよりも菌糸飼育は種類が限られるので、合わない種類に使ってしまうと死亡してしまいます。
菌糸飼育ができる種類
- 国産オオクワガタ
- ギラファノコギリクワガタ
- アンタエウスオオクワガタ
- ヒラタクワガタ
- ニジイロクワガタ など
カブトムシなどは菌糸飼育は絶対にNGです!!
菌にまかれる
菌糸ビンはきのこ菌がおがくずに回って出来ています。
きのこ菌が強すぎると幼虫がきのこ菌に負けてしまい死亡することがあるんです。
 少年
少年きのこ菌って悪さもするんだね。扱いが難しそう・・・
対策としては、ある程度育った幼虫(2令~)を菌糸ビンに投入することで、菌にまかれて死亡するリスクを減らすことができます。
初令幼虫を菌糸ビンに投入する方法はあまりおすすめできません。
流れとしては、幼虫が成長するまで発酵マットで育て、2令幼虫なったところで菌糸ビンに入れる。
といった流れがいいのではないかと思います。
カワラ菌糸などは菌の成長がものすごく早いので自分で菌糸をボトルに詰めた場合は、詰めてから3週間ほど置いて菌の成長が緩やかになってから幼虫を投入したほうがいいでしょう。
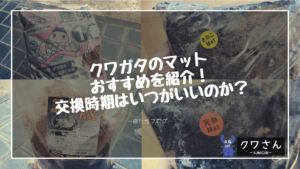
添加剤
菌糸ビンには、添加剤も入っています。
この添加剤が幼虫に合わない場合にも死亡することがあります。
特に添加剤を調合して自作する場合は気を付けないといけません。
販売している菌糸ビンについては、実験を繰り返し作っている商品なので、添加剤の量も絶妙に調整してあります。
 クワさん
クワさん菌糸ビンは大きく育つ可能性を秘めていますが、死亡するリスクがあることを覚えておきましょう。
温度管理
菌糸ビンだけに限ったことではありませんが、温度管理を怠ると菌糸の劣化やうまく菌が回ってくれないことがあります。
菌糸が劣化している状態↓↓

菌糸ビンが劣化した状態で使い続けると幼虫が死亡することがあります。
菌糸ビンの温度管理は18~25℃で管理を行うことがいいでしょう。
そのほかにも劣化する原因はいくつかありますが、温度管理は必ず必要になりますので、適切な温度管理をしましょう!
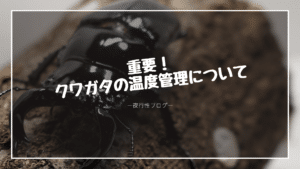
菌糸ビンって何だろう‐まとめ
「菌糸ビンって何?」や菌糸ビンのメリットやデメリット、「菌糸ビン飼育で幼虫が死亡する?」についてお伝えしてきました。
菌糸ビンはクワガタを大きくする大きなメリットがある一方で、扱いを間違えると死亡するリスクもあります。
幼虫を大切に育てたいと考えるなら、発酵マットでの飼育をおすすめします!
 クワさん
クワさん筆者はほとんど発酵マットで飼育しています。
今回の記事を参考にカブクワ飼育を楽しんでくださいね!
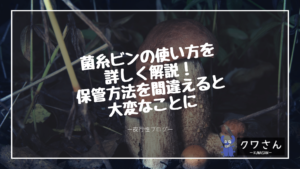
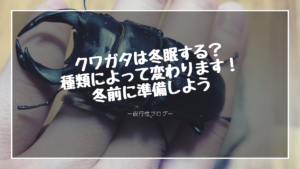
飼育グッズ、ちゃんと選べてますか?
僕が実際に使って
「これはマジで便利」
「もっと早く知りたかった…」
と思った、初心者にも安心のおすすめ飼育グッズをまとめました。
失敗を減らしつつ、カブクワとの暮らしがもっと楽になります👇
\ブリード初心者必見!!/

また、現在販売中のカブクワ生体リストも随時更新しています!
僕が育てている生体の中から、現在販売中のカブトムシ・クワガタを一覧にまとめました。
BASEもしくは、ヤフオクのどちらかでご購入ができます👇
\最新の生体リスト/
現状はネット販売のみになりますが、近い方なら直接手渡しも可能です。
質問などありましたらお気軽に下記リンクより、お問い合わせください👇


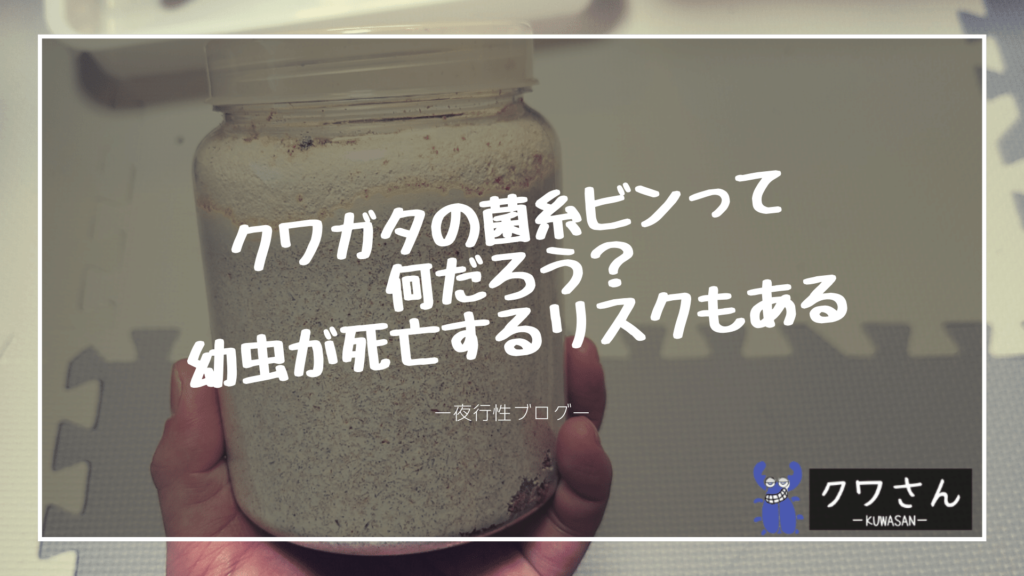

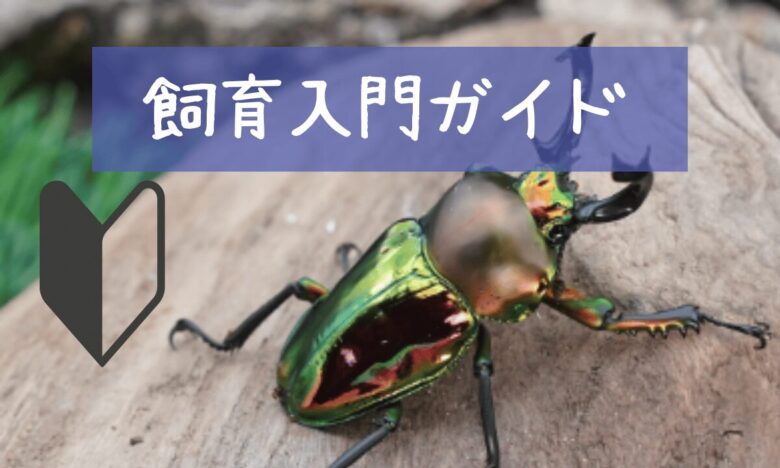
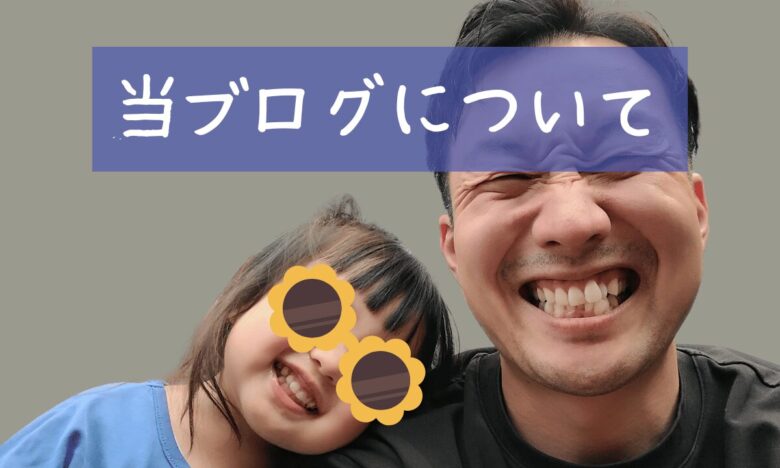
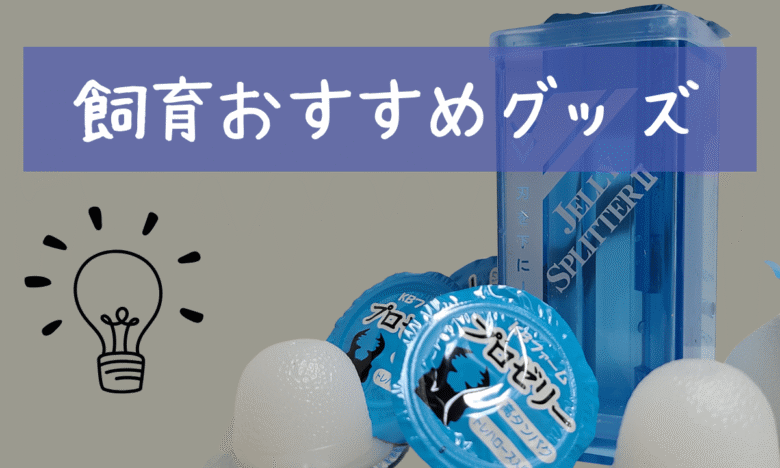

コメント